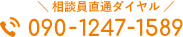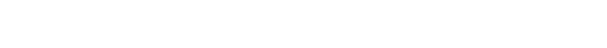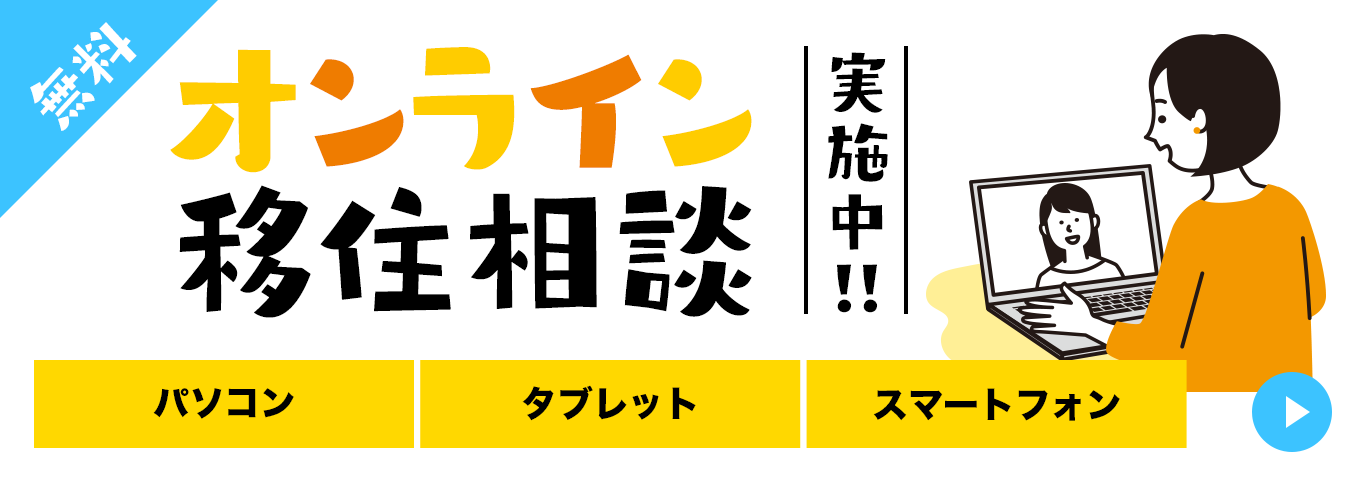こんにちは。東京から淡路島に移住して4年目になる小林です。
2025年4月より、移住者ブログの執筆を担当することになり、前回のブログ記事で簡単にご挨拶させていただきました。
よろしければこちらもあわせてご覧ください。
移住してからというもの、先輩移住者としてなにかとセミナーに呼んでいただいたり、こうして記事の執筆をすることも増えたり、自身の移住体験を振り返る機会も多くありました。
その都度、東京での暮らしと現在の暮らしを比較して、違いを言語化したり、自分でも気づかなかった多くの発見があったりします。
数ある変化の中でも、今回は特に僕自身の「価値観の変化」に焦点を当ててみたいと思います。
冒頭で結論をまとめるとすると、それは、都会で暮らしていた頃の自分の「消費思考」から、ここ淡路島で芽生えた「創造思考」への大きな転換があった……そんなお話です。
超便利!「サービスメニュー化された都会」の暮らしは実際のところ最高ですよ。

移住しておいてなんですが、僕が20代のころに住んでいた東京という街はとても楽しかったです(笑)
東京は、お金を払えば何でも手に入る便利な街。
朝のコーヒーから夜の食事、日用品の買い物から週末のレジャーに至るまで、あらゆるものがサービスとして最適化され、提供されています。

困ったことがあっても少し手を伸ばせば、専門家による質の高いサービスがすぐに受けられる。自分であれやこれやと工夫しなくても、快適に、そして効率的に暮らせる環境でした。
それはそれで素晴らしいことであり、その恩恵を十二分に享受していたことは間違いありません。
忙しい日々の中では、時間を買う感覚でサービスを利用することも多く、それが都会的なスマートさだとさえ感じていました。
しかし今振り返ると、その便利さの裏側で、どこか
- 「暮らしの主導権をサービスに委ねていたのではないか」
- 「自分自身で何かを生み出したいなと思っても環境がないな」
と感じる瞬間があります。
今思えば、お金があれば体験できるメニュー化が進んだ環境で、完成されたものを手に入れることに慣れ、受動的な感覚が染みついていたのかもしれません。
「不便」と嘆くか、「余白」として楽しむか。

一方、淡路島の里山暮らしでは、「ないものが多い」のが現実です。笑
都会のように24時間営業の店が至るところにあるわけでもなければ、電車を20分も乗ればなんでも揃うような街があるわけでもありません。
というか、電車はないですし……。
東京時代に比べたら、端的に言って「不便」の何ものでもありません。
最初は戸惑うこともありましたが、それが逆に
- 「じゃあ、自分たちで作ってみよう」
- 「こうすればできるんじゃないか」
という能動的な発想、いわば「創造思考」への転換を促してくれました。
その最たる例が、移住の大きなきっかけともなった古民家のリノベーションです。

専門業者に全てを任せるのではなく、自分たちの手でできることはやろうと決め、壁を塗ったり、床を張ったり、時には解体作業にも挑戦しました。

(まぁ、予算がないからなんですけどね)
もちろん、プロの職人さんの指導や助けを借りながらですが、汗を流し、知恵を絞り、少しずつ形になっていく過程は、何物にも代えがたい喜びと達成感を与えてくれました。

その過程で
「床の下はこんな作りになっているんだ」
「壁ってこうしたら簡単に作れるんだ」
「工具ってこうやって使うと便利に使えるんだ!」
と、家の構造を理解したり、触ったことのない工具が使えるようになったりと、できることが増えていくのもまた幸福度が上がっていくんです。

なので、最初は「不便だな」と感じていたことが、いつしか「工夫のしがいがあるな」「創造性を試される面白い課題だな」と捉えられるようになって気さえする。
良いように言えばこの島では、生活そのものを、自分たちの手でDIYしていく楽しさがあります。
(大前提として、面倒くさいことが多いことには変わりはありませんが)
創造がもたらす、暮らしの深みと新たな繋がり

東京での「消費中心の暮らし」と、淡路島での「創造中心の暮らし」。
この二つを比較してみると、単にその価値観の違いが生まれることだけに留まりません。
そう。誰しもに創造的な余白がある(ないものが多いとも言う)中で、面倒くさい「不便さ」もあると、やっぱり誰かを頼ったりしないとコトが前に進まないわけですね。

つまり、暮らしの中で人との関わりがとても深くなる。
例えば、古民家のリノベーションや集落での生産活動・景観維持活動を通じて、地域の方々とのコミュニケーションが格段に増えました。
「ここはどうしたらいい?」「こんな道具があるよ」とアドバイスをいただいたり、時には一緒に作業を手伝ってもらったり。一つの目標に向かって共に汗を流す中で、自然と会話が生まれ、関係性が深まっていくのを感じます。
都会では希薄だったご近所付き合いも、ここではごく自然な形で育まれています。

不便さの中にこそ、工夫や創造の喜びがあり、そして人との新たな繋がりが生まれる。
この「創造する暮らし」は、効率や利便性だけでは測れない、人間らしい温かみと手応えを僕たちの生活にもたらしてくれている…と、そんな風に感じています。
「創る」ことで見つける、自分らしい豊かさ
「消費」から「創造」へ。
この思考の変化は、淡路島での里山暮らしが僕に与えてくれた、最も大きな贈り物の一つかもしれません。
もちろん、都会の利便性や洗練されたサービスを否定するつもりは全くありません。
しかし、自分たちの手で何かを生み出し、暮らしを形作っていく中で得られる達成感や、そこから広がる人との繋がりは、以前の僕が想像していた「豊かさ」とは少し違う、けれど確かな温もりを持ったものです。
移住は、単に住む場所を変えるだけではなく、自分自身の価値観や生き方を見つめ直す人生の岐路でもあります。
もしこれを読んでいるあなたが、日々の暮らしに何か物足りなさや、受動的な感覚を抱いているとしたら、ほんの少しでも「自分で創ってみる」という視点を取り入れてみるのはいかがでしょうか。
それは、新しい自分や、新しい豊かさへの扉を開く、小さな一歩になるかもしれません。
このブログが、そんな風に暮らしのあり方を考える、ささやかなヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
P.S. この記事を書いている5月のGWも、民泊の開業に向けてDIYを進めていました!
(子どもたちに手伝ってもらいながら…笑)